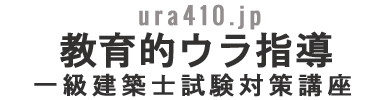製図対策受講者たちの「今の声」を紹介!
教育的ウラ指導の通信添削講座では,受講者皆様に,課題ごとにアンケートに回答していただいています.受講者皆様に学習内容を共有していただくためです(回答すると他の受講者の回答を閲覧できます).
8/28現在,第1課題Bの学習(復習)を進めているところですが,インプット課題である《第1課題A-1と第1課題A-2》のアンケート回答の一部を紹介します.
第1課題A-1の学習を経て
理解できたことや身に着いたと思うこと
◇庁舎建築に求められる基本的な機能・構成を理解することができました。細かい部分では、特別職エリアの収め方、議場の座席のレイアウトなど、エスキスや図面作成の段階で分からなかった部分が解消されました。
◇とにかく何もわからないということがわかった。まずはエスキスのやり方の手順を覚えるのが肝心だと理解した。
◇行政部門と議決部門の諸室のレイアウトや動線の基本が理解できた。
◇プログラム図の作成意図が理解できたと思います
◇庁舎のプログラム図、議決部門・特別職エリアのセキュリティの考え方が理解できました。
◇利用者、議員、行政、管理者の動線を理解することができた。
◇二方向避難、セキュリティラインの設定の仕方など庁舎特有の課題を肌で感じられた。
◇課題を解くことで庁舎の構成を理解することができた。事務室は利用者動線しか考慮していなかったが、職員動線も分けて計画することを確認できた。
◇庁舎を利用する人々の動線を理解できた。また、セキュリティについても配慮が必要なことを知ることができた。
◇製図試験における作図ルールと課題文との関係を把握することができた。
◇エスキスの短縮の考え方。図面チェックに時間を回すための工夫。
第1課題A-2の学習を経て
理解できたことや身に着いたと思うこと
◇基準階型のエスキスの考え方、ゾーニングを2方向分けるためのコアの打ち方、吹抜けの計画、基準階型のウツワの検討方法
◇免震構造についての知識
◇基準階型のエスキスの進め方、免震構造の作図表現
◇階数自由指定のボリュームチェックの一例を理解した。
◇コミュニティ施設のように、眺望や方角を気にしなくてよい。基準階の考え方。
◇詳細なプランニングに入る前の大ボリュームでの検討がいかに大事か。ここで各階のコマ数とウツワのコマ数を合わせてコアと動線計画が見通せないなら成立しないし、見通せるならかなり合格に近づく。
◇特別職と議会のエリアを最上階にゾーニングすることが理解できた。
◇敷地条件で隣地に駐車場があった場合の考え方。免振層の計画のポイント。
◇セキュリティの考え方。なるべく動線の起点となる共用部エリアを集約して、徐々に特定の人しか入れないエリアに移っていくゾーニング構成にすると、まとまりやすいことが分かった。
※回答内容の意図や趣旨が変わらないように文章を一部編集して掲載しています.ご了承ください.